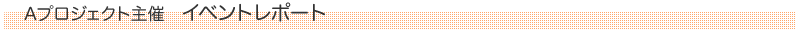
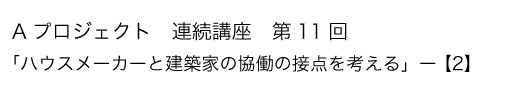
 「家」の成り立ちとその原点
「家」の成り立ちとその原点 住まい手が物でつくる空間
住まい手が物でつくる空間
ここまでで話が終われば大変素晴らしいレクチャーになるのですが、本職は建築家なので自分もつくらなければいけない。これは1990年に初めてつくった広島の「狐ヶ城の家」です(資料21-22)。

住宅団地の一番端の不定形な敷地に建てた家です。このときに考えたことは、家も重ね着したり着替えることができないかということでした。15cm角の材木でグリッドに格子を組んで、必要に応じて様々な障子を建てこんでつくる家です。家の中には決まった名前の部屋はなくて、全体が大きな広縁のようになっています。格子の中に色々な透過度の障子が入っていて、必要に応じて空間を隔てるものがグリッドにはまっています。夏や冬や季節に応じて住まい手は自分の好きなところで寝られます。
昨年、23年ぶりに取材したいと『住宅特集』から依頼があり、改めて撮影したらいろいろな物が置かれていて、住み手が住んできた状態ができあがっていました。そこに暮らす人が好きな物を持ち込んで、自分の空間を物によってつくり出すことも、工業化住宅を捉え直す上でもう一度真剣に考え直す必要があると思います。
これは次につくった「バウムハウス」(資料23-24)です。

上一間下一間しかない小さな木賃アパートです。誰が住むか分からない賃貸住宅を、8割方の人が満足するキッチン、8割の人が満足する洗面所、8割の人が満足する下駄箱というようにつくっても、0.8×0.8×0.8×…と掛けていくとたちまち半分以下の人しか満足できないものになってしまう。そのように考えて、中途半端なものはつくらずに徹底的にミニマムにつくったアパートです。その代わりに天井を2.6mと高くして、暮らす人は自分の物を持ち込んで住人の世界をつくることができる。引越すときは全てトラックに積んで持っていけばたちまちもぬけの殻に戻る。この経験から、住まいは空箱的なものが良いんじゃないかという考えに至りました。
この「バウムハウス」は物で中身をつくる家ですが、それを3軒建ててくれという施主が現れました。3つそのままつくるわけにはいかなかったので、敷地に合わせて上下で互い違いになる長屋を考えました。一見外から見ると大き目な2階建てにしか見えませんが実際には4層あります。中から見るとコンクリートの箱でできていて完全に外断熱です。空っぽのロフト付きハウスで住む人の物で埋め尽くされます。僕がつくった空間というよりは住人がつくった空間。建物の骨格は半分くらいは規定しているけれども、住み手が自分でインナーウェアを運んでくる家です。
「Zig House/Zag House」はずっと後回しにしていた自分の家です(資料25-27)。

左手が両親の住まいで右手が僕と妻と子供が住む家です。片方は一階が低くて2階が高い、もう片方は1階が高くて2階が低い、足し合わせると屋根の高さは同じで真ん中にポーチがある二世帯住宅です。この家の骨組みは集成材で、それ以外は奥多摩の間伐材でできています。飯能に間伐材を圧着して編成材をつくる工場があり、7.5cmにスライスしたものを耐震壁に、6cmにスライスしたものをスラブにしています。二階はこの上に石膏ボードを一枚敷いて、フローリングを貼っただけというスラブの構成です。形がジグザグしているので「Zig House/Zag House」と呼んでいます。今はここに母がいろんなものを持ち込んでいますから同じ写真は撮れなくなっていますが、全部運び出せばもぬけの殻に戻ります。もともとこの場所に住んでいたので、既存の木をよけてつくったらこんな形になりました。家自体はモンゴルのゲルのように着たり脱いだりできないですが、木のおかげで夏は日差しや視線を遮ってくれますし、冬に葉が落ちれば家の中まであたたかい日差しが入ります。
これは世田谷の宇奈根につくったコンクリート造一戸建ての住宅です(資料28-29)。

農地が宅地化され家がどんどん建って行く敷地で、この家の窓はどうしたら良いかを考えました。私の答えは、普通窓が開くところには窓をつくらないで、普通窓が開かないところに窓をつくることで、隣と視線が干渉しないようにできないかと考えました。普通なら窓を開けそうなところに窓がないだけで隣との干渉をひとつブロックできる。まだらな窓のおかげで隣との関係はこちらが開けっ放しにしていてもあまり干渉しない。住宅地の住宅はみんな同じ位置に窓があるために、窓と窓が向き合ってカーテンを閉めざるを得ないですが、相手と微妙にずれているだけで必ずしもカーテンが必要ではなくなる。
これは稲毛につくった歳を召したファッションデザイナーが一人で住むための家です(資料30-32)。

独り住まいになるとワンルームに近い形をつくることができます。ワンルームにたった一枚壁が入るだけでできている家です。壁一枚しかなくてスカスカなんですけど、物を上手につくれば直接面と向かわないような関係ができる。この家は実際にカーテンをつけないまま住まれています。このワンルームは友だちのシェフを招いて食事会をしたり、人と人が出会うためにある。もちろん一人のときは住まいですが、人を呼んで招いたときに機能する空間です。人を招いて人が入っている状態が家なんですね。
最後に、千葉県の八千代につくった環境学者の田辺新一さんの家です(資料33)。

環境学者の田辺先生ですからいろいろ実験的な試みはしたい。けれども、とかくエンジニアが自邸をつくると実験装置のような家が出来てしまうのですが、彼はそれはしたくないということで、僕のところに依頼がありました。ここではまず、ふつう住宅の南側の面はたいがい大きな窓が開いているものですが、ここには換気口だけがついています。いろいろなタイプの換気口があり、換気口の見本市のようになっています。田辺さんは24時間換気やシックハウスの専門家ですから、いろいろな換気口をシンボルにしました。全体構成は入れ子状で真ん中にコアがあり物置になっています(資料34-35)。

その周りに居住空間があります。変型した敷地に会わせた三重入れ子です。コアの周りに玄関や階段があり、そこを抜けると和室やバスルーム、二階ではリビングをぐるっと回り込むとキッチンが奥に見えます。ご夫婦お二人なので、寝室も極めて簡単に仕切られてできています。南の代わりに東側に窓があって、夏の日が高い時期には朝方を過ぎると日差しが入らなくなる。ここでは何重かの皮膜をつくるというよりは、まぶしいときに人が額に手をかざように、建築の一部がそのようにはたらけばルーバーやブラインドを使わなくても日よけができるのではないかと考えました。ふつうの住宅地と対峙して塀も建てずに建っていますが、開放的でありながら外からはあまりディスターブされない、そういう家のつくり方ができないかと考えていました。
こうして自分がつくってきた住宅を振り返りながら総括的にいうと、環境や外界にたいしてある構えを持っているというのが基本形です。できることなら近くにある材料で、その土地にある構法でできると理想的。中身は家族の形態や住まう人のスタイルはどんどん変わって行きますから、建築でつくり込まれているよりはそこに運び込まれた物でできあがっている方がいいと感じています。それが協働のヒントになるかどうかはこの後にお話しいただければと思います。

住宅団地の一番端の不定形な敷地に建てた家です。このときに考えたことは、家も重ね着したり着替えることができないかということでした。15cm角の材木でグリッドに格子を組んで、必要に応じて様々な障子を建てこんでつくる家です。家の中には決まった名前の部屋はなくて、全体が大きな広縁のようになっています。格子の中に色々な透過度の障子が入っていて、必要に応じて空間を隔てるものがグリッドにはまっています。夏や冬や季節に応じて住まい手は自分の好きなところで寝られます。
昨年、23年ぶりに取材したいと『住宅特集』から依頼があり、改めて撮影したらいろいろな物が置かれていて、住み手が住んできた状態ができあがっていました。そこに暮らす人が好きな物を持ち込んで、自分の空間を物によってつくり出すことも、工業化住宅を捉え直す上でもう一度真剣に考え直す必要があると思います。
これは次につくった「バウムハウス」(資料23-24)です。

上一間下一間しかない小さな木賃アパートです。誰が住むか分からない賃貸住宅を、8割方の人が満足するキッチン、8割の人が満足する洗面所、8割の人が満足する下駄箱というようにつくっても、0.8×0.8×0.8×…と掛けていくとたちまち半分以下の人しか満足できないものになってしまう。そのように考えて、中途半端なものはつくらずに徹底的にミニマムにつくったアパートです。その代わりに天井を2.6mと高くして、暮らす人は自分の物を持ち込んで住人の世界をつくることができる。引越すときは全てトラックに積んで持っていけばたちまちもぬけの殻に戻る。この経験から、住まいは空箱的なものが良いんじゃないかという考えに至りました。
この「バウムハウス」は物で中身をつくる家ですが、それを3軒建ててくれという施主が現れました。3つそのままつくるわけにはいかなかったので、敷地に合わせて上下で互い違いになる長屋を考えました。一見外から見ると大き目な2階建てにしか見えませんが実際には4層あります。中から見るとコンクリートの箱でできていて完全に外断熱です。空っぽのロフト付きハウスで住む人の物で埋め尽くされます。僕がつくった空間というよりは住人がつくった空間。建物の骨格は半分くらいは規定しているけれども、住み手が自分でインナーウェアを運んでくる家です。
「Zig House/Zag House」はずっと後回しにしていた自分の家です(資料25-27)。

左手が両親の住まいで右手が僕と妻と子供が住む家です。片方は一階が低くて2階が高い、もう片方は1階が高くて2階が低い、足し合わせると屋根の高さは同じで真ん中にポーチがある二世帯住宅です。この家の骨組みは集成材で、それ以外は奥多摩の間伐材でできています。飯能に間伐材を圧着して編成材をつくる工場があり、7.5cmにスライスしたものを耐震壁に、6cmにスライスしたものをスラブにしています。二階はこの上に石膏ボードを一枚敷いて、フローリングを貼っただけというスラブの構成です。形がジグザグしているので「Zig House/Zag House」と呼んでいます。今はここに母がいろんなものを持ち込んでいますから同じ写真は撮れなくなっていますが、全部運び出せばもぬけの殻に戻ります。もともとこの場所に住んでいたので、既存の木をよけてつくったらこんな形になりました。家自体はモンゴルのゲルのように着たり脱いだりできないですが、木のおかげで夏は日差しや視線を遮ってくれますし、冬に葉が落ちれば家の中まであたたかい日差しが入ります。
これは世田谷の宇奈根につくったコンクリート造一戸建ての住宅です(資料28-29)。

農地が宅地化され家がどんどん建って行く敷地で、この家の窓はどうしたら良いかを考えました。私の答えは、普通窓が開くところには窓をつくらないで、普通窓が開かないところに窓をつくることで、隣と視線が干渉しないようにできないかと考えました。普通なら窓を開けそうなところに窓がないだけで隣との干渉をひとつブロックできる。まだらな窓のおかげで隣との関係はこちらが開けっ放しにしていてもあまり干渉しない。住宅地の住宅はみんな同じ位置に窓があるために、窓と窓が向き合ってカーテンを閉めざるを得ないですが、相手と微妙にずれているだけで必ずしもカーテンが必要ではなくなる。
これは稲毛につくった歳を召したファッションデザイナーが一人で住むための家です(資料30-32)。

独り住まいになるとワンルームに近い形をつくることができます。ワンルームにたった一枚壁が入るだけでできている家です。壁一枚しかなくてスカスカなんですけど、物を上手につくれば直接面と向かわないような関係ができる。この家は実際にカーテンをつけないまま住まれています。このワンルームは友だちのシェフを招いて食事会をしたり、人と人が出会うためにある。もちろん一人のときは住まいですが、人を呼んで招いたときに機能する空間です。人を招いて人が入っている状態が家なんですね。
最後に、千葉県の八千代につくった環境学者の田辺新一さんの家です(資料33)。

環境学者の田辺先生ですからいろいろ実験的な試みはしたい。けれども、とかくエンジニアが自邸をつくると実験装置のような家が出来てしまうのですが、彼はそれはしたくないということで、僕のところに依頼がありました。ここではまず、ふつう住宅の南側の面はたいがい大きな窓が開いているものですが、ここには換気口だけがついています。いろいろなタイプの換気口があり、換気口の見本市のようになっています。田辺さんは24時間換気やシックハウスの専門家ですから、いろいろな換気口をシンボルにしました。全体構成は入れ子状で真ん中にコアがあり物置になっています(資料34-35)。

その周りに居住空間があります。変型した敷地に会わせた三重入れ子です。コアの周りに玄関や階段があり、そこを抜けると和室やバスルーム、二階ではリビングをぐるっと回り込むとキッチンが奥に見えます。ご夫婦お二人なので、寝室も極めて簡単に仕切られてできています。南の代わりに東側に窓があって、夏の日が高い時期には朝方を過ぎると日差しが入らなくなる。ここでは何重かの皮膜をつくるというよりは、まぶしいときに人が額に手をかざように、建築の一部がそのようにはたらけばルーバーやブラインドを使わなくても日よけができるのではないかと考えました。ふつうの住宅地と対峙して塀も建てずに建っていますが、開放的でありながら外からはあまりディスターブされない、そういう家のつくり方ができないかと考えていました。
こうして自分がつくってきた住宅を振り返りながら総括的にいうと、環境や外界にたいしてある構えを持っているというのが基本形です。できることなら近くにある材料で、その土地にある構法でできると理想的。中身は家族の形態や住まう人のスタイルはどんどん変わって行きますから、建築でつくり込まれているよりはそこに運び込まれた物でできあがっている方がいいと感じています。それが協働のヒントになるかどうかはこの後にお話しいただければと思います。
門脇
古谷先生ありがとうございました。伝統的な家のレクチャーが非常に印象的でした。家というのは古来、風土や環境と応答しながらできているということをご説明いただきました。古谷先生が指摘していたのは、本来住宅は自律的で完結的なものではないということで、古谷先生自身もそのような住宅をつくることを目指されている。つまり住宅は、外部に関しては環境や風土、内部に関しては住まい手の存在があってはじめて、住宅たり得るということだと思います。そのような視点から改めて住宅を眺めてみると、住宅自身も、人や環境のインターフェイスとして、それぞれとインタラクションしながら環境の一部になっている。しかし現在の住宅は、たとえば外部環境と切り離されても「快適な室内環境」が得られるような方向に進んでいます。つまり古谷先生が指摘されたような住宅の姿は、おそらく日本の住宅が工業化する過程で、失ったもののひとつではないかと考えることもできるでしょう。
つづいて第二部の対話に入って行きたいと思いますが、住宅産業が今日的にどのように位置づいているのかを確認することから始めたいと思います。そして最終的には、住宅産業がこれからどうあるべきかという話につなげたい。それが明らかになれば、ハウスメーカーや建築家はその中でどのような役割を担って行くべきなのかも見えてくることでしょう。まずは難波先生から、古谷先生のお話のご感想も交えながらご意見をいただきたいと思います。
次回[3]へ続く。
つづいて第二部の対話に入って行きたいと思いますが、住宅産業が今日的にどのように位置づいているのかを確認することから始めたいと思います。そして最終的には、住宅産業がこれからどうあるべきかという話につなげたい。それが明らかになれば、ハウスメーカーや建築家はその中でどのような役割を担って行くべきなのかも見えてくることでしょう。まずは難波先生から、古谷先生のお話のご感想も交えながらご意見をいただきたいと思います。
次回[3]へ続く。






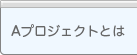
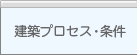
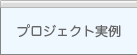

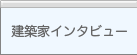
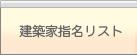
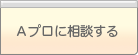
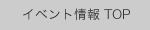


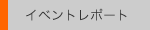
 イベントリポート
イベントリポート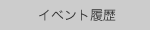






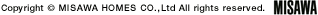
今日は改めて住宅だけピックアップしてお見せしたいと思います。最初は家の観察から始めましょう。これは大学で授業するときによく使うスライドで、マリオボッタ事務所にいたときに住んでいたスイスのルガーノからアルプスの麓に入ったところにある石積みの民家です(資料13)。
石の組積造ですが、その材料は裏の山から採ってきました。ごく近所の材料なので、自動的に周囲に調和した色になっている。形はもちろん人工的で、人の手で運んで積み上げられる大きさに細かく刻んでつくられている。窓はまわりを漆喰で塗り固めてテーパーをつけて斜めにしていますが、これは日当りの悪い谷間でできるだけ長い時間日照を確保するためです。同時にあまり大きく窓をあけると断熱性能が下がるので、最小限の窓にするための工夫でもあります。
次に軸組造の住居はどうなっているかを見ていきましょう。これは韓国のヤンバン(両班)住宅の障子窓です(資料14)。
さらに暖かい地方のタイ北部の民家(資料15)では、壁はほとんど竹格子になっていて、寝室だけ竹に包まれていて窓はひとつもない。このように、およそ住まいというものは全てその近所にある材料で出来ていて、その土地の風土で培われたものが反映されていることがわかります。
なぜこんなところから話を始めるかと言うと、住宅の今後を考えたときに、もうちょっと素朴なところから家の成り立ちを捉え直してもいいのではないか、と思うからです。これからの住宅のイノベーションの原点は、土着的なものを振り返ったところにもありえるのではないか。その極めつけがモンゴルのゲルです(資料16)。
1995年にモンゴルで見た遊牧民のゲルですが、プロペラで発電してパラボラアンテナで衛星放送を観ています。水も電気もガスも、インフラの全くないところに一家族だけで暮らしていて、世界情報に接している。冬場にはマイナス40度にもなるような気候の中で死なずに生存する能力をもっている。中はまるきりのワンルームです(資料17)。
移動式住居なので当然ですが、畳んで移動するために簡潔なつくりになっています。そこにベッドや家具やものが置かれて出来上がっている空間。ここに暮らす家族は全員雑魚寝をします。まったくプライバシーのない空間です。なぜそういうことが可能かと言うと、広大な草原に暮らす彼らにとって家は人と会うためにある場所だからです。一日の仕事が終わり家族と会い、知り合いと会い、たまにはふいの旅人と会う、人と会うための場所なのでその中には仕切りはいりません、ということをこの家は教えています。
もうひとつ、この家は環境的にみても面白い。モンゴル人の衣服はデールという民族衣装です。夏はその下はTシャツ一枚で、冬になるとセーターを着てデールの内側に毛皮を貼り付けたりします。つまり重ね着です。モンゴルの民族衣装は王侯貴族も含めて全てこの形式で、夏は薄着、冬は厚着。面白いことに家でも同じことをやります。夏のゲルはあばら骨が見えるほど薄着をしていて、裾は空けて風が抜ける状態。冬になるとフェルトを3重にして、ドアにも綿入れをして裾にはスパッツを履かせて隙間風を防いでいる。同じ家の骨組みを持ちながら、夏には薄着、冬には厚着をする家です。ここにも何かこれからの工業住宅をイノベートしていく上で非常に大きなヒントがあるように思います。
最後に日本からもひとつ。沖縄本島の本部町備瀬の集落です。防風林で有名な集落です(資料18)。
沖縄の住まいはもとより暑い気候のため非常に開放的な住まいです。これはその住宅で猫が寝ている写真です(資料19)。
猫は一番快適な場所をみつける名人です。良く見ると奥にお父さんとお母さんも寝ています。ここに気持ちのいい風の通り道があるのでしょう。めいめい居心地のいいところに陣取っている、そういうシーンです。なんとも素晴らしい建築の姿だなあと思います。加えて、この写真のもうひとつ示唆的なところは、真夏の午後2時の暑い盛りに全員寝ているということです。つまり真夏の盛りに仕事をしようとするから窓を閉めてエアコンをつけなきゃいけなくなってしまいますが、夏の盛りには昼寝。極寒の冬には家族で冬眠する。そう考えれば住宅もだいぶ違ったものになるかもしれません。
これは僕が経験した世界で最も美しい国際会議ですが、チェンマイの森の中でアジアの16カ国の建築家が集まって教育の話をしています(資料20)。
ときどき強い日差しが射し込んでしまうので、ボランティアの学生が傘を動かして光線が当たる人の前だけ傘をさすという、このたった2枚の傘で十分というものです。我々が自然の中が好きで、住みたいなと思っても、われわれはモンゴルの人と違ってひ弱なので、我が身ひとつで生きて行くというわけにはいかない。その時にはこの傘のように、最小限の人工的な要素が人間と自然の間にあればいいのではないか。それが建築ではないかと思います。