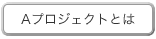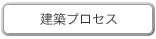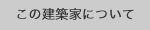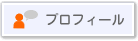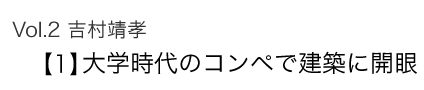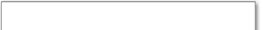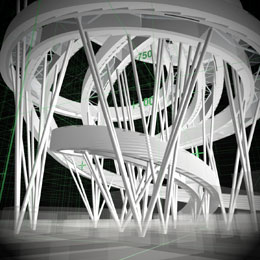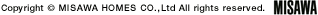�v���_�N�g�f�U�C�i�[�ɂȂ肽������
�v���_�N�g�f�U�C�i�[�ɂȂ肽�������\�\�Ȃ����z�̂ق��ɐi�܂ꂽ�̂��A���̂��������݂����Ȃ��̂���܂��������������̂ł����B
�g��
�l�����܂ꂽ���m���̖L�c�s�̓g���^�̊�Ə鉺���ŁA�ʂ������w�Z���g���^�{�Ђ̂����e�ł����B�قڑS�����g���^�̏]�ƈ��̎q���Ƃ����悤�ȏ�Ԃł�����A���m�J���`���[�Ƃ������A�I���̂Ȃ��ώ����ɑ��ꂵ���������Ȃ���������ł�����ǂ��A����ŁA�o�ׂ�҂��S�A�����̃J���[���������i�ŁA�ʎY�������̂ւ̓��������B���̎Ԃ��������E���̓��H���삯����Ȃ��Ƃ킭�킭���Ȃ��璭�߂��L��������܂��B�����������ꂩ��A�����̓v���_�N�g�f�U�C�i�[�ɂȂ肽���Ǝv���Ă��܂����B���Z�����炢�ɂȂ�ƁA�悭���Ƃ����ڂ��Đ}���قł���炵���{��T������A�f�U�C���n�̃V���|�W�E�����ɍs�����肵�Ă��܂����ˁB�����������Ă��邤���ɐi�H�����߂鎞���ɂȂ��āA���炽�߂ăv���_�N�g�n�̃f�U�C�i�[�̌o�������Ă݂�ƁA���z�w�ȏo�g�̐l�������肵�āB����Ŏ����͌��z�w�Ȃɍs�����̂��Ǝv������ł��܂����B���z�w�Ȃɍs���v���_�N�g�f�U�C�i�[�ɂȂ邽�߂̃R�[�X�������āA������������������ɈႢ�Ȃ��Ǝv���Ă�����ł��B
�\�\���z�A���邢�͌��z�Ƃɓ���ĂƂ������Ƃł͂Ȃ�������ł��ˁB
�g��
�ł͂Ȃ��ł��ˁB�c�ɂł������ɓ���ɂ����f�U�C���n�̎G���͂킴�킴����w�ǂ����肵�Ă��āA�t�B���b�v�E�X�^���N�̐V��͒m���Ă�����ǁA���E�R���r���W�G�͒m��Ȃ��Ƃ����A���n�Ȃ��������悭�킩��Ȃ����Z���ł����B�G���Ɉ��V����A�������Y����A�����a������Ȃǂ����グ���Ă������Ƃ��L���Ɏc���Ă܂�����A���z�ƂƂ����E�\�����邱�Ƃ͗������Ă����͂��ł����A�����̓v���_�N�g�f�U�C�i�[�ɂȂ���̂��Ǝv���Č��z�w�Ȃɍs�����Ƃ��������ł��B
�\�\����ő���c��w�ɓ����āA�H�ƃf�U�C�����猚�z�̕��Ɉӎ����V�t�g���Ă������̂͂����炢�ł����B
�g��
�l�͒��r���[�Ȋw���ŁA���̂������D�G�Ƃ����킯�ł��Ȃ����S�R�ł��Ȃ��Ƃ����킯�ł��Ȃ��B���ƂȂ�����Ȃ��Ƃ������A��������Ă��m�M�����ĂȂ��悤�ȂƂ��낪����܂����B���w��1991�N�Ŋw���̑��Ƃ�95�N�ł����A�����͖l��������Ȃ��Č��z�E�S�̂����݂��Ԃ������ƌ����Ă��ǂ���������܂���B�o�u���̎c�荁�͂������ǂ��A��͒Z���B�����]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������������邯�ǁA�s����͌����Ȃ��B�����������͋C�Ɉ��������Ă��Ƃ������A�g���������Ă��܂����悤�ȂƂ��낪����܂����B
�Ȃ̂ŁA�w������͖{���Ɍ��z�w�Ȃŗǂ������낤���Ƃ����^������Ƀm���}�����Ȃ��Ă��������ł��B�����������Ă��邤���ɑ�w�@�i�w�����߂鎞�������āA���̔N�V�����ł����ÒJ���͌������ɓ��邱�Ƃɂ��܂����B���ꂪ���z�Ƃ����ƌ����������������Ƃ��đ傫�������B�ÒJ�搶�����C��������ł������A�������̃X�^�b�t�̕��X���w���̖l�����ƔN��߂��������Ƃ������āA�������������ӑR��̂Ƃ��������łƂ����������Ȃ��ƂɎ��g�݂܂����B�l����ԍŏ��Ɋւ�点�Ă�������̂͂������f�B�A�e�[�N�i���j�̃R���y�ł����B�P�������ꂽ�ɓ��L�Y����̌�����2000�N��̑�\��ɂȂ�܂������A�l����P�킵�ĂQ�������������܂����B
���������f�B�A�e�[�N�F���E��T���ʂ�Ɍ��}���فA�M�������[�Ȃǂ̕����{��
�Ȃ̂ŁA�w������͖{���Ɍ��z�w�Ȃŗǂ������낤���Ƃ����^������Ƀm���}�����Ȃ��Ă��������ł��B�����������Ă��邤���ɑ�w�@�i�w�����߂鎞�������āA���̔N�V�����ł����ÒJ���͌������ɓ��邱�Ƃɂ��܂����B���ꂪ���z�Ƃ����ƌ����������������Ƃ��đ傫�������B�ÒJ�搶�����C��������ł������A�������̃X�^�b�t�̕��X���w���̖l�����ƔN��߂��������Ƃ������āA�������������ӑR��̂Ƃ��������łƂ����������Ȃ��ƂɎ��g�݂܂����B�l����ԍŏ��Ɋւ�点�Ă�������̂͂������f�B�A�e�[�N�i���j�̃R���y�ł����B�P�������ꂽ�ɓ��L�Y����̌�����2000�N��̑�\��ɂȂ�܂������A�l����P�킵�ĂQ�������������܂����B
���������f�B�A�e�[�N�F���E��T���ʂ�Ɍ��}���فA�M�������[�Ȃǂ̕����{��
�\�\�ÒJ����I���R�Ƃ����̂́H
�g��
�l��]�����Ă��ꂽ�̂͌ÒJ�搶������������ł���i�j�B�ق����Ă��̂��Ă��炦�Ȃ������Ǝv���܂��B����c�͐v�̉ۑ肪2�{���ĂɂȂ��Ă��āA���p�قƂ��w�Z�Ƃ��A�����錚�z��N4�v����u�v���}�v�ƁA2�T�ԂɈ�x���炢�̃n�C�y�[�X�ŏ����ȉۑ�������Ă����u�v���K�v�Ƃ����̂������āA�����́u�v���K�v�ƌ����Ă�����ł����A����2�{���Ẳۑ�̂����A�l�́u�v���}�v�����ŁA�u�v���K�v�͓��ӁB�ÒJ�搶�͂R�N���́u�v���K�v��S������Ă����̂ŁA�����������R�ɁA�ÒJ���ɍs�����̂Ǝv������ł��܂����B���܂�i�H�ŔY�ތo�������Ă��Ȃ���ł��B
 ���������͂������f�B�A�e�[�N�̃R���y
���������͂������f�B�A�e�[�N�̃R���y�\�\�ÒJ���ɓ����āA���낢��Ƃ��ꂽ���ł����f�B�A�e�[�N�̃R���y�̑̌��Ƃ����̂��ӎ���ς��Ă�����ł͑傫�������̂ł��傤���B
�g��
���Ǝv���܂��B����ߒ��ł̐搶�Ƃ̋c�_�͔��Q�Ɏh���I�ł������A���ꂪ����Ӗ��\�z���ĕ]�������Ƃ����I�}�P�����Ă��āc�c�ł��A���ӋC�ɂ��A�R���y�Ɏ��g��ł���Œ��́u�œ|�ɓ��L�Y�v�Ƃ������Ȃ������Ă�����ł���i�j�B
�\�\�ɓ����o�Ă���Ƃ����͈̂Ⴂ�Ȃ��Ɨ\�z���Ă��āA�������ɏ����Ȃ��ƁA�ƁB
�g��
�����Ȃ�ł��B����ŘA���O��Ő���オ���Ă��āA�u�œ|�ɓ��L�Y�v�̑z��ⓚ�����Ă����B�܂�������k�Ƃ������A������ł܂����̂悤�ȑ啗�C�~�ł����A�ӂ����J���Ă݂���{���ɂ���ɋ߂����Ƃ��N�����Ă��āB�����܂����B����Ō��z���ĂȂʔ�����Ȃ����Ǝv���Ă��܂����B
�\�\��̓I�ɂ͂ǂ������ӂ��ɂ͂܂肱��ł�������ł����B
�g��
���f�B�A�e�[�N�̌ÒJ�ĂƂ����̂́A���̒�Ď��̂ɁA���z�̌��_��A�Ƃ������A����ԂƂ̓K�Ȑ��ݕ����ɂ���Ď���Ԃ̑��ݍ��������߂��Ƃ����X�g�[���[���g�ݍ��܂�Ă��܂�����A�l�̒��Ԃ���������ɉ�������čs���܂����B���Ԃ���́A���z���Ė{���ɕK�v�Ȃ́H�Ƃ����w���ɂ��肪���Ȗ��ӎ����ǂ����Ă��ʂ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��āB�����P�{����Ƌ�Ԃ��ł���ƌ�������ǂ��A���Ȃ����Ă��A���Ƃ��Βn�ʂɕ`���ꂽ�o�X�P�b�g�{�[���̃R�[�g�����Č��z�I�ȍS���͂�����B���̂Ƃ��Ă̌��z���Ȃ������Ƃ��Ă��A�ӎ��̒��Ő��܂�Ă͏����A�����Ă͐��܂�Ƃ������Ƃ��J��Ԃ��悤�Ȍ��z�A�I�A���ۓI�Ȍ��z������B���̉\���ɌX�|���邠�܂�A�܂������肪�����Ȃ��Ȃ��Ă�����ł��B���������A�ۑ�Ń}���K��`���Ē�o�������Ƃ�����܂��B�}�ʂ�͌^�͂Ȃ��B����͓������ŋ����Ă��������Ă���������_���C�ɓ����Ă���܂����B
�\�\�����܂ł��R���Z�v�`���A���ȃA�v���[�`�ŁA���m�̐��E�ɂ͍s���Ȃ������킯�ł��ˁB
�g��
���f�B�A�e�[�N�̃R���y���������̂�95�N�ł��B���̔N�͌��z�ւ̐M����h�邪���悤�ȏo�����������������āA���Ƃ��I�E���^�����ɂ���A�̎��������̂ЂƂł��B��w�ł͌ÓT�@�����z�̏@���I�ȋ@�\�ɂ��ċ����܂����A�I�E���̐M�҂͓��Ƀf�W�^���K�W�F�b�g�����ăr�f�I�����Ȃ����E��ڎw���Ă���B���_�m��I�ɕ���Ă���킯�ł͂Ȃ����̂́A���z�ɂ܂��������l�����o�����Ȃ��l�X�̑��݂�����Ɉ�ۂɎc��܂����B���ꂩ���_�E�W�H��k�Ђ������āA�������H�⍂�w���z�Ȃǐ�ɉ��Ȃ��Ǝv������ł������̂��ӂ�ӂ�Ɠ|�Ă��܂����B����܂Œ~�ς��Ă������z�ւ̕s�M���̂悤�Ȃ��̂��A���������ɔ����̉��ɂ��炳��Ă��܂����Ɗ����܂����B����ŁA���̂܂܂��Ⴞ�߂ȂƂ������o���͂����苤�L�ł��āA�ÒJ�Ẵ|�W�e�B�u�Ȑ�Ԃ��ɂȂ����Ă����B��H���Ȃ���悤�Ȋ��o������܂����B
�ÒJ�Ă̓��e�́A���Ō����Ƃ���̌g�ѓd�b�݂����Ȃ��̂������Ċٓ����U�Ă��炢�A���̒[���A�܂����ԂɌ������\�������肵�Ă��炤���Ƃɂ���āA����Ԃ̕��͂�蕡�G�ł�荬�ׂƂ��Ă����Ƃ��Ă����������邱�Ƃ��ł���A�Ƃ������̂ł����B���z�́A�\���s�\�ȏo�����ɖ������ꂽ�o�U�[���̂悤�ȏ�ƂȂ�킯�ł����A���ꂪ���z�Ɏc���ꂽ�B��̉\������Ȃ����Ƃ����Ă�������ł��B��������ȏ��[���͂܂��Ȃ������킯�ł�����ǂ��A�������������B�W������`�������ƂŁA�X�b���D�ɗ�����Ƃ������A���z�������ɂ킽���đ��݈Ӌ`������������Ƃ����m�M�邱�Ƃ��ł����̂ł��B����Ō��z���ʔ����Ȃ����������ł��ˁB
�ÒJ�Ă̓��e�́A���Ō����Ƃ���̌g�ѓd�b�݂����Ȃ��̂������Ċٓ����U�Ă��炢�A���̒[���A�܂����ԂɌ������\�������肵�Ă��炤���Ƃɂ���āA����Ԃ̕��͂�蕡�G�ł�荬�ׂƂ��Ă����Ƃ��Ă����������邱�Ƃ��ł���A�Ƃ������̂ł����B���z�́A�\���s�\�ȏo�����ɖ������ꂽ�o�U�[���̂悤�ȏ�ƂȂ�킯�ł����A���ꂪ���z�Ɏc���ꂽ�B��̉\������Ȃ����Ƃ����Ă�������ł��B��������ȏ��[���͂܂��Ȃ������킯�ł�����ǂ��A�������������B�W������`�������ƂŁA�X�b���D�ɗ�����Ƃ������A���z�������ɂ킽���đ��݈Ӌ`������������Ƃ����m�M�邱�Ƃ��ł����̂ł��B����Ō��z���ʔ����Ȃ����������ł��ˁB
�\�\�����ł͂܂����ƁB
�g��
�͂܂��Ă��܂��܂����ˁB���ƌ�̓v���_�N�g��O���t�B�b�N�Ȃnj��z�ȊO�̓��������Ȃ����ƒ��炭�v���Ă��܂������A����Ŗ����͂Ȃ��Ȃ�܂����B�l��͗��j�I�Ɍ��ăR���s���[�^���͂��߂Ďg��������Ȃł͂Ȃ��ł����A���z�w�ȂŌl�I�Ƀp�\�R���������Ă���l�͂܂������h�ŁA�R���s���[�^�������炷�Љ�̕ω��ɂ��Đ��m�ɘ_���悤�Ƃ����@�^�͂��܂�Ȃ������悤�Ɏv���܂��B�ǂ��炩�Ƃ����ƃC���[�W��s�B�������ł��Ă���Ƃ��A�����Ă����Ƃ��A�E�F�u������s��^�ȖԂ��Ƃ��B���̂������Ȃ��Ƃ��낪����Ԃ̓����Ȃ̂ɁA�u���E���ǂ̉𑜓x�Ƃ��A�V���R���`�b�v�̖͗l�Ƃ��A�����Ȏ��̂Ɉ��������Ă��܂��Ă����B����l�炪�l�����悤�ȁA�����I�ȋ�Ԃ��Ȃ����ƂŌ������\���A�b�v���A�f�[�^�x�[�X�����i�ނƂ������b�ƁA�}���\�i���ޖ@�I�ȕ�����Ԃ̐����p�Ƃ��d�˂āA�����炵�����z�̎p��͍�����Ƃ����A�v���[�`�͍����L���ȉۑ肾�Ǝv���܂��B
 �炍�̒����w��
�炍�̒����w���\�\�ÒJ���ł́A���f�B�A�e�[�N�ȊO�ł͂ǂ����������̂����ꂽ��ł����B
�g��
���Ƃ��u�n�C�p�[�X�p�C�����v�Ƃ����v���W�F�N�g��S�����܂����B�����炍�̒����w�����Ă���ǂ��Ȃ邩�Ƃ����X�^�f�B�ł��ˁB�[�l�R���e�Ђ��Q������������o�āA�ŏI�I�ɁA�p�I���E�\�����ƃ����E�R�[���n�[�X�ƌÒJ���͂����̒����w���z�̒�Ă��܂Ƃ߂Ă�����ăV���|�W�E�����������ł���B���̌ÒJ�Ă�S�����āA�����w�̐^��Ƀr�����Ƃ���������Đ炍�܂œ��B����Ƃ����Ă�����܂����B
�\�\�Ƃ���������Ƃ����̂́H
�g��
�܂��炍�̒����w�Ƃ����ƁA���͂⌚�z�ł͂Ȃ��ēs�s�ƌ��Ȃ��ׂ�����Ȃ����ƍl���܂����B�����Ō������z�Ƃ����̂́A24�K�ɍs���̂�48�K�ɍs���̂��P�K�ŃG���x�[�^�[�ɏ���ă{�^�������������ŁA�K�ƊK�̊Ԃɂ܂������W���Ȃ��悤�ȍ��̒����w���z�̂��Ƃł��B���̂܂܂ł́A�ǂ��܂ŋK�͂�傫���������ēs�s�I�Ȃ��̂ɂ͂Ȃ肦�Ȃ��̂ł����A�����ėׂ̊K�ɍs����悤�ɂ��ĊK���m�̊W����������Ԃ�Ƃ܂��ɂȂ��Ȃ����ƍl���܂����B�܂�c�ɂ̂т��Ȃ��ĉ��ɂ̂т�ׂ��A�ƁB���ɂ̂т�Ƒ��ӕ~�n���͂ݏo�Ă��܂��킯�ŁA����͂ł��Ȃ����猋�ʓI�ɂ��邮��ƂƂ�����������킯�ł��B
�\�\����͂ǂ������r���f�B���O�^�C�v�ō\�z���ꂽ��ł��傤�H �������Ƃ������ɂȂ�Ȃ��悤�ȃr���f�B���O�^�C�v�Ȃ�ł����B
�g��
�v���O�����͓��肵�Ă��܂���B���w�����ł͒n��ƈقȂ�ł��낤�C��𗘗p���ē���Ȗ���͔|����_�����������炢���̂ł͂Ȃ�Ęb������܂����B�x�O�܂ŕ������s�s���̂��̂Ƃ������C���[�W�ł��B�p�r�͓��肵�Ȃ�����ǁA�����牽�܂ŒZ�����݂݂����ȕs���Y�̃X�L�[�����Ă��Ă��܂��B���Ō����J���I�P�{�b�N�X�Ƃ��C���^�[�l�b�g�J�t�F�ɋ߂��悤�Ȋ����ŁA�Z���ԓ���̏ꏊ���L���邽�߂̗������x�����āA�����ŐQ���肨���C�ɓ�������{��ǂ胊�r���O�ł��낢���肷��B���L���������ɐݒ肵�Ȃ��ŁA�݂�Ȃł����ɏZ�ݍ���ł��钴���w�݂����Ȃ��̂��Ă��Ă��܂��B
�\�\���̒Z�����݂Ƃ����l�����͍��̋g������̂��d���ɂȂ����Ă���悤�Ɏv�����ł����A����͋g������̃A�C�f�A��������ł����B
�g��
���ƂȂ��Ă͂ǂ�ȃv���Z�X�Ő��܂ꂽ�A�C�f�A���������܂Ŋo���Ă��܂��A�������Ɍ��݂܂Ōp���I�ɍl���Ă���ۑ�ł��B�o�u���œy�n�̒l�i�������������Ƃ��W���Ă��邩���m��܂��A�s�s��Ԃɐݒ肳�ꂽ���L�̌`�����d������Ǝv�����B�����͂��傤�ǁA�J���I�P���Ȃ���n����҂悤�Ȑ��������A���Ɋ����n�߂�ꂽ�������������A�����ƓK���ɁA�Z���Ԃ�����L���Ă܂��ʂ̏ꏊ�ɍs���݂����ȁA�����������C�t�^�C�����\�Ȃ�Ȃ����ƁB�����̗V�q���̂悤�Ȋ����B�ÒJ���ł̓����S���̃Q���̌���������Ă��܂�����A������e�����Ă��邩������܂���B�����S���͓y�n�ɏ��L�����ݒ肳��ĂȂ����ŁA�y�n�̐�L�Ƃ����T�O���Ȃ��B�����������x���A�����̂ǐ^�Ŏ�������ʔ�����Ȃ����ƁB
 ��w�@�œ������M
��w�@�œ������M�\�\�ÒJ���œ������̂Ƃ����̂�����Ƃǂ��Ȃ�܂����B
�g��
�������ɂ͌���99�N���炢�܂ł�����ł����A����͂��傤�ǃC���^�[�l�b�g�̕��y���Əd�Ȃ�܂��B��ʓI�ȑ�w������y�Ɉ����悤�ɂȂ��������ł��B�Ȃ̂ŁA���Z�p�����z�̋�Ԃ��ǂ̂悤�ɕς���̂��Ƃ������Ƃz���������������Ƃ܂Ƃ߂Ă��ǂ��Ǝv���܂��B
�\�\�����āA���������e�[�}���A���z�̂Ȃ��ł́A��[�I�ɂ��Ƒ��������Ɏ��g�߂��ƁB
�g��
�����ł��ˁB���f�B�A�e�[�N�͂��̍ł�����̂ŁA�����Ō����̂��ςł����A������������������Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B���������ʓI�ɑ��̒����e�[�}�ɂȂ����B����S���Ȃ����E�C���A���E�i�E�~�b�`�F���́w�V�e�B�E�I�u�E�r�b�g�x�Ƃ����{�������ꂽ�̂�96�N�ł�����A���̑O�N�̋c�_�Ƃ��Ă͐��x�����������Ȃ��B
�\�\���z�Ə��Z�p�Ƃ����e�[�}�ɑ�������������g�݂������������ʂ��グ���A�������������݂����Ȃ��̂͌��z��{�i�I�ɃX�^�[�g�����Ŕ��ɑ傫�������ł����B
�g��
�������Ǝv���܂��B���M�ɂȂ�܂����ˁB
2010�N12��24���A�g�����F���z�v�������ɂĎ��^�B����́y2�z�ɑ���